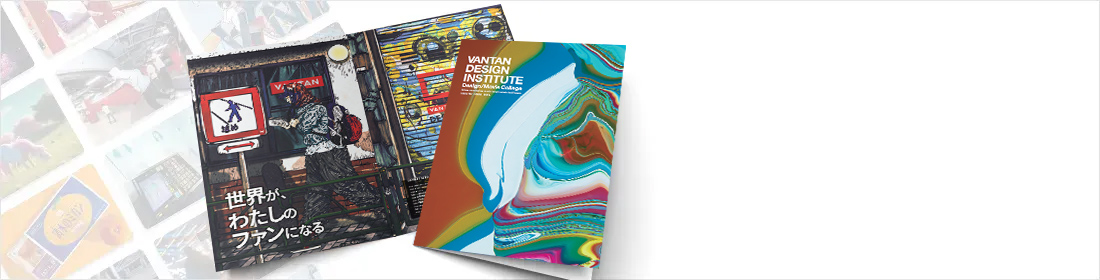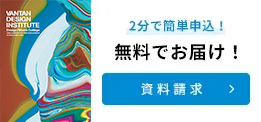バンタンデザイン研究所卒業生のアーティスト集団「DWS」スペシャルトークセッション【バンタンデザイン研究所】

日本伝統技術「墨流し」の技法を改良し再解釈した独自のスタイルを「色流し(しきながし)」と名付け、東京を拠点に国内外でも活躍するアーティスト集団 DWS(DIRTY WORKERS STUDIO)。
バンタン卒業生の「岩本 薫さん(イラストレーター:DWS)」、「新井 緑さん(墨流し作家/ TattooArtist:DWS / The Good Cat Scratch)」、「森 洸大さん(アートディレクター / 色流し家 / デザイナー:DWS / MILLENNIUM PARADE / PERIMETRON)」の3名によるトークセッションを公開!

---ものづくりの世界に進もうと思ったきっかけ
岩本薫(以下:薫) 映画だね。ターミネーター2やプレデターには影響を受けていて、「 これどうやって作っているんだ?」「自分でも作ってみたいなー」と考えたりしていたのが、ものづくり
の道に進む一番のきっかけだったかもしれないです。
森洸大(以下:洸) 小学生の頃に木の棒とビニールテープで作ったライトセーバーが原体験になっている気がする。中学の時には Slipknot(全メンバーがマスクを被る米メタルバンド)が大好きで見様見真似でマスクを作ったり。とにかく物作りはずっと好きだったのと、頭は良くないし、かといってスポーツでもトップに行けるほどではなかったので、自分には物作りしかないと思っていました。
新井緑(以下:緑) 明確な理由は思い出せないけど、母が音楽家で祖父が金物職人、祖母は大工家系で、母には小さい頃から「手に職をつけるといい」と言われて育ちました。その影響もあり、小さい頃からものづくりは大好きで、職人に憧れを持っていたのもあり、ものづくりの道に進みたいと感じた様に思います。
---学生時代の思い出
緑&薫:サマーセミナーの学生スタッフかな。チームの仲間たちと作品を作ったり、参加してくれる後輩の子たちを楽しませるために企画したり、 楽しいことや辛いこともあったけど、思い出としては一番残っていますね。
洸:卒業制作展もすごく思い出に残ってます。それまでライバルのような存在だった同学年のみんなと最後はまとまって一つのショーを作り上げるっていう体験は、そう出来るものじゃないし、今の自分を作ってくれている大事な経験だったなと思います。

---DWS結成の経緯や秘話
緑:結成からもうじき 10 年になります。当時お世話になったバンタンのスタッフさんがきっかけでしたね。 サマーソニックのブースでなにか出展してみないかと提案をいただいて、集まったメンバーが、私と洸大、 薫でした。そこでマーブリングを使ったボディペイントをやったのが結成のきっかけで、今の活動の原点になります。
---なぜマーブリング(色流し)なのか?
緑:Black Light Visualsという、体にマーブリングをする集団のYouTubeを見ていて、私達なりに挑戦してみたらすごく楽しかったのがきっかけでした。
洸:それからマーブリングは(諸説あるが)「墨流し」という古くから伝わる日本の伝統技法が元になっているのを知って、活動を快諾してくれた Black Light Visuals との差別化を図るためにもあくまで「マーブリング」ではなく日本由来の「墨流し」を主軸に、従来の技法よりも色濃く染められるよう現代的にアレンジを加え「色流し」と名付けた独自の技法で活動していくことを決めました。個人的には当時やっていた造形や特殊メイクという具象的な表現方法に不自由さを感じていたこともあって、抽象的で瞬間的な手法の魅力がしっくりきた事も大きかったですね。
---DWSとして一番の思い出はありますか?(俺達きたなと思った瞬間)
薫:トルコに行ったことじゃないかな?
洸:トルコだね!トルコで開催されるフェスのスポンサーブランドの方から、SNS を通じてお誘いをもらったのが初めての海外の仕事で。「 海外で仕事をする」というのも目標の一つに掲げていたので、あの時の嬉しさは鮮明に記憶に残っていますね。

---活動をやめようと思ったことは?
洸&薫:やめようと思ったことはないかな。
緑:色流しをやめようと思ったことはないけど、チーム活動が辛い時期はあって、何度か挫けそうにはなりました(笑)。 でも、チームだったから自分も成長ができて、メンバーが洸大と薫だったから一緒に続けてこられたんだと感じています。
洸:一人だったら絶対無理でしたね。3人だから続けられた。薫のため、緑のためって思えた瞬間が一番自分を強くさせてくれたし、そのおかげで続けてこられたと思います。
---作品を制作する上で大切にしていること
緑:大事にしていることは沢山あります。一つあげるなら、墨流しは誰がやっても何となく綺麗に見えるアートなんです。 だからこそ自分の作品を制作する中で、常に自分のスタイルとセンスを磨き続けることを試行錯誤しながらやってきました。
薫:自分のスタイルを出すこと。そのスタイルを守ること。 これを一番に意識しています。
洸:自分を疑い続けることと、「 この一枚で人生を変えてやる」と思う事。それほど向き合っても、世の中は残酷なもので全然人生は変わらないんですけどね。それでもそう信じて作り続けていればいつか「あの作品を見て何か一緒に作りたいと思った」という人に出会えたり「 夢が見つかりました。人生が変わりました」と言ってくれる人が現れたりして、振り返ればいくらか自分の人生も変えてくれている事に気づかせてもらえたりします。そのために目の前の仕事や作品一つ一つに対して、そこまで向き合えているのか、人生を変える一枚を作れているのか、常に自分を疑うこと。この気持ちが無くなった時はもう自分は潮時だと思います。それくらい、何よりも大切にしてます。

---今後の展望
洸:また海外で仕事したいね。
緑:行きたいね!よくばりだけど、世界中回ってみたい(笑)。チームとしての目標は、日本伝統技術の墨流しを元にしているこの技術を、DWS ならではの「色流し」として確立させて、さらに高いレベルまで持っていけるように技術を磨くこと。個人としては人生をかけてやってきた墨流しを、もっともっと極めて、やれる限りペイントをし続けたい。他にも興味がある事はできる限り挑戦して、 人生楽しんで生きていけたら最高です。
洸:意外と自分がこうなりたいというのがあるようでなくて。ありがたいことに周りにはドでかい野望を持ってたり、 ものすごい才能を持ってるヤツがたくさんいて、その仲間たちが夢を叶える、幸せになる瞬間を見ていきたい。それが自分の幸せでもあるし、その中で本当に自分がやりたいことも生まれていくんじゃないかなと。そういう想いで今はがむしゃらに活動して、その結果この世代一体で日本をまたかっこよくしていけたらいいなと思ってます。
薫:自分のお店を持ちたい。お店というか隠れ家(アジト)のような場所。ファッションや音楽も好きなので、雑貨や洋服を販売してみたり、 好きな時に仲間が遊びに来て、 話したり、制作したり、音楽聴きながらコーヒー飲んでのんびりしたりできる。そんな場所を作ってみたいです。
---今回バンタンのパンフレット制作にあたって依頼があった時の感想、どんな思いで引き受けたか、どんなイメージで制作したか、伝えたい思いなど
緑:すごく光栄だった!母校のパンフレットを担当させてもらえるなんて本当にありがたいことです。
薫:( 中ページイラストを担当。)自分の好きなことに対して常に勉強をし続けて欲しいという思いを込めてイラストを描きました。参考にした浮世絵があって、その絵には「常に勉強をし続ける」「わずかな時間でも惜しまず勉強する」という意味があり、自分で選んだやりたいこと、好きな事は恥ずかしがらずに勉強して日々精進してほしいという思いを重ねました。
緑:( 表紙/裏表紙を担当。)依頼をいただいた時、バンタンデザイン研究所はいろんな分野(カルチャー)があり華やか、対象的にバンタン芸術学院は落ちついた印象。 というそれぞれのイメージをもたせながら、 2 冊を並べて一枚絵で繋がる様にして欲しいというオーダーがありました。対照的な印象を一枚の絵で表現するのには苦戦しましたが、パンフレットをみる方々がワクワクしながらページを開いてもらえる様なイメージを想像して作品を制作しました。

---好きなことを仕事にする上で大切にしてること
薫:自分を信じて、何があってもめげずに立ち向かう気持ちを大切にしてほしいです。
緑:薫と同じ想いです。私が今この仕事をできているのは、チームや家族、 周りの人達のおかげで、 それに運が良かったのもあります。 けど運を掴めたひとつの要因は、やりたいことを熱望し続けてきたからこそ、動き続けたことがすごく大きかったように感じます。沢山失敗もして挫けそうになったし、DWS を始めてからも一本では食べていけない時期も長かったけど、信じて一歩一歩続けてやってきた。もちろん長い間、 周囲からの心配も感じていましたが、DWS 結成 8 年目を過ぎた頃から「続けてきて良かったね」と言われることが多くなり、周囲の反応も変化しました。挫けそうになったり、周囲の反対があったり、道に迷うことも沢山あると思うけど、自分を信じること、やり続けること、動き続けることが大切だと感じています。
洸:緑の話した通り、結局はやめずに続けることですね。DWSの活動をやめたいと思ったことはないけど、物作りは本当に過酷で辛いし、全部やめてしまいたくなることなんていくらでもある。それでも周りのみんなと未来の自分が幸せになるために、いつかいつかと思いながら今を頑張る。その、単純だけど強い気持ちだけでやめずにやってこれた。スキルを磨くことはあとからで良くて、まずは自分がやめないために何を大事にしたらいいのかを見つけてあげることが大切だと自分は思ってます。